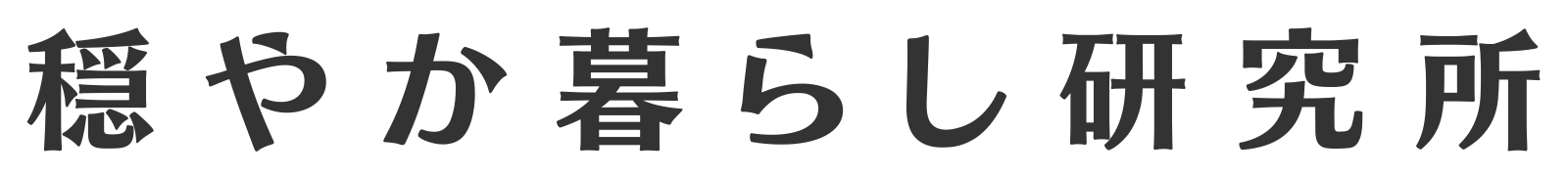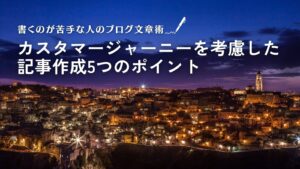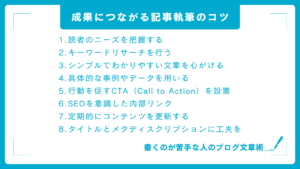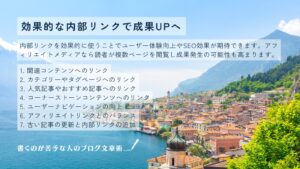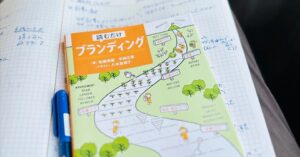今朝、YouTubeを眺めていたときのことです。
いつも聴いている友人(吹奏楽団で音楽をしている)のチャンネルに、新しいBGM集が公開されていました。
そのBGMは、音楽生成AI「SUNO」で作られたもの。
作業用に流しながら仕事を始めたのですが、ふとした瞬間、心の琴線に触れる旋律に出会い、すっかり心を奪われてしまいました。
「AIで作られた音楽なのに、こんなにも感情を揺さぶられるのか!」
この体験をきっかけに、実際の音楽家たちはAIをどう捉えているのか気になり、調べてみることにしました。
AI作曲をめぐる音楽家の声を調べてみた
AIで作曲ができるようになった時代。
実際の音楽家たちは、この変化をどう捉えているのでしょうか。
リサーチを進めると、大きく二つの立場に分かれることが見えてきました。
ひとつは「AIを創作の相棒や新しいインスピレーション源として歓迎する声」。
もうひとつは「人間らしい表現を脅かす存在だ」として強い懸念を示す声です。
以下では、それぞれの代表的な意見を紹介しながら、ぼく自身のコメントも添えて整理していきます。
肯定派:AIは創作を広げるツール
AIの登場を前向きに受け止める音楽家たちもいます。
彼らは、AIを「創作を助ける相棒」や「新しい発想をもたらす存在」として歓迎しています。
例えば、自分専用のAIアシスタントを開発して活用する人、AIを“追加の作曲家”と表現する人、業界全体の変革に必要だと語る人など。
ここでは、Imogen Heap、Björn Ulvaeus、Daniel Bedingfield、will.i.am といったアーティストたちの視点を紹介します。
Imogen Heap(イモジェン・ヒープ)
Imogen Heap(イモジェン・ヒープ)はAIを積極的に活用し、自ら「Mogen」というAIアシスタントを開発しています。
AIを“創造性を軽くする道具”と捉え、インスピレーションの触媒として歓迎する立場です。
ただし「トレーニングデータの透明性や著作権の配慮が不可欠」とも述べています。
(参考:Wikipedia – Imogen Heap)
 奥成大輔
奥成大輔AIを道具として自ら手懐ける姿勢は、とても大人の音楽家らしいと感じました。
「便利だから使う」ではなく「どう使えば健全か?」を問いながら前に進む姿勢は、ぼくたちがブログやアフィリエイトにAIを導入する際にも重なると思います。
Björn Ulvaeus(ABBA)
ABBAのビョルンは、AIを「追加の作曲家」と呼び、新しいアイデアを引き出すパートナーとして評価しています。
ただし、「クリエイターの権利が守られてこそ意味がある」と、制度面の重要性も強調しています。
(参考:People – ABBA Musician Bjorn Ulvaeus Says He’s Using AI)



ABBAのような時代を築いた人が、AIを拒絶せず柔軟に迎えているのは印象的です。
過去の栄光に安住するのではなく、新しいテクノロジーを積極的に取り込む姿勢に学ぶものがあります。
Daniel Bedingfield
「AIは音楽の未来だ」と断言するベディングフィールド。
同時に「変化に対応しないと取り残される」とも語り、業界の構造改革やアーティストへの公平性も課題に挙げています。
(参考:The Guardian – Daniel Bedingfield says AI is music’s future)



AIはただの便利ツールではなく、業界そのものを揺さぶる存在になっている。
この「未来からの圧力」を冷静に受け止めることは、音楽だけでなくどんな仕事にも共通していると思います。
will.i.am(ウィル・アイ・アム)
彼は「純粋なアーティストにはAIの影響は少ない」としながらも、マネージャーや法務、監査担当、レーベル幹部といった周辺の職種には大きな影響があるかもしれないと語っています。
つまり、音楽そのものよりも“ビジネスの現場”に変化が訪れる、という視点です。
(参考:New York Post – Black Eyed Peas star predicts which jobs may go extinct thanks to AI)



たしかに「作る人」より「売る人」「守る人」が大きく変わっていくのかもしれません。
音楽の世界も、Webメディアの世界も、AIで一番揺さぶられるのは周辺の仕組みや役割なのでしょう。
懸念派:AIは音楽を脅かす存在?
一方で、AIに対して強い危機感を抱く音楽家たちも少なくありません。
彼らは、AIには「苦しみや感情がない」として、人間らしい表現が失われることを危惧しています。
また、著作権やクリエイターの権利保護、さらには音楽の価値そのものを脅かしかねないという指摘もあります。
ここでは、Nick Cave、Paul McCartney、Roger Daltrey らベテラン勢の意見を中心に見ていきます。
Nick Cave
Nick CaveはAIによる音楽を強烈に批判しています。
「アルゴリズムには苦しみも感情もない」とし、人間の生々しい表現こそが音楽だと主張しています。
(参考:The Australian – Nick Cave responds to AI in songwriting)



Caveの言葉は、AIに期待を寄せる空気に一石を投じるものです。
確かに“痛み”や“救い”といった感情は、人間が生きる中で経験してこそ生まれるもの。
AIがそれを本当に表現できるのか…… 問い続ける価値があると思います。
Paul McCartney
ポール・マッカートニーはAIに懸念を示し、著作権やクリエイターの権利を守るために政府の介入すら必要と訴えています。
(参考:The Sun – AI is here to change our lives forever but we MUST protect musicians)



「制度が追いつかないうちに技術だけが進む」…… これはWebの世界でもよくあること。
守るべきものを守るために、ルールづくりが急務なのだと思います。
Roger Daltrey ら他のベテラン勢
AIは音楽の価値を下げかねない、と危惧する声も根強いです。
2025年には複数のミュージシャンが「サイレント・アルバム」で抗議の意思を示しました。
(参考:The Sun – AI is here to change our lives forever but we MUST protect musicians)



音楽を人生と重ねてきた世代にとって、AIは脅威に見えるのも自然なこと。
ただ、その抵抗感自体が「人間のリアルな声」であり、AIには真似できない表現でもあるのだと感じます。
自動車とAI、電子計算機に通じる暮らしへの影響
ここでひとつ、ぼく自身の体験からの例えを挟ませてください。
自動車も昔は“機械仕掛け”が中心でした。
しかし今や、電子制御なくしては語れない存在になっています。
ぼくにとって自動車は、単なる機械製品ではなく、暮らしや人生に多大な影響を与えてきた存在です。
便利さや効率だけでなく、移動や体験そのものを変え、人生の風景を作ってきました。
同じように、電子計算機…… つまりコンピュータもまた、登場した当初は「計算を助けるための機械」にすぎませんでした。
ところが今では、インターネットやスマートフォンを通じて暮らしのあらゆる場面を支える、欠かせない基盤となっています。
AIもそれと同じだと思うのです。
創作活動においてAIをどう取り入れるか…… これは単なる技術の話ではなく、暮らしや生き方に関わる選択なのだと感じます。
まとめ:AIは「敵」でも「救世主」でもなく
AI作曲に対する音楽家たちの意見は、大きく「共創ツールとして歓迎する派」と「本質を脅かすと警戒する派」に分かれています。
ぼく自身は、この2つは矛盾していないと思います。
AIは「便利なツール」であると同時に、「人間らしさを改めて問い直す存在」だからです。
ブログ運営やアフィリエイトの世界でも、AI記事は氾濫しています。
その中で“人間にしか書けないこと”をどう残すのか…… 音楽家たちの議論は、そのまま自分たちへの問いにもなると感じます。
あとがき:記事の作り方について
この記事を書くきっかけは、友人のYouTubeチャンネルで流れていたAI生成BGMに心を奪われた瞬間でした。
「AIでも、こんなに人の心を揺さぶる音楽ができるのか」と感じたのが出発点です。
その後、各音楽家の声を調べ、自分なりのコメントを添えて整理しました。
記事の仕上げには、いつものようにChatGPT(=チャッティーナ※)の力を借りています。
※ ぼくの考えや仕様を反映し、創作や記事づくりを一緒に歩む相棒として、親しみを込めて“チャッティーナ”と呼んでいます
ぼくのやり方は、まず自分のオリジナルな情報や感情を出発点にし、それをChatGPTに編集・整理してもらうというスタイルです。
AIに丸投げするのではなく、人間の声を残したまま、読みやすく磨き上げる。
音楽家がAIを“共創のパートナー”とするように、ぼくもまたAIを「書く相棒」として使っています。
創作活動をする人と生成AI、この対比はこれまでもずっと関心を持って見守ってきましたし、今後も気になるテーマです。